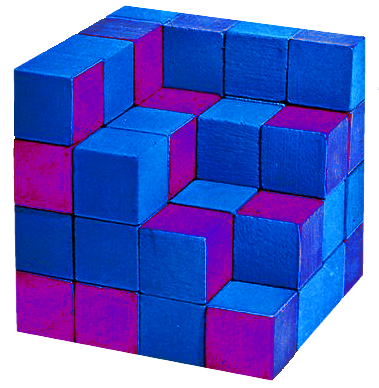FEECO Vol.4に掲載した『日本発個人的音楽二十五連』というディスクガイドページには、ここ10年の日本在住者によって作られた音源を選出している。以下に5枚。
アンドリュー・マッケンジー(The Hafler Trio)は、音響を用いた意識変革法と匿名性を利用したイメージ戦略をもって、世界が情報戦下にあることを証明し続けてきた。しかし、mp3に象徴される複製文化の進行から時代との齟齬を感じたアンドリューは、結論として不特定多数へのアクセスからセルフ・メディケーション的な自己変革にたどりつく。大阪在住のソニック・アクショニスト、ルドルフ・エバーは、86年12月にSchimpfluch-Gruppe(シンプフルク・グルッペ)を立ち上げた時から現在まで、あらゆる体験の現場たる「個人の内面」にフォーカスし続けている点でアンドリューよりも慧眼であった。
その心理学と科学の二点に立脚するルドルフの「psychophysicaltestsand trainings」なる概念は、サイバネティクスの脱オカルト化を図るように日々研究が重ねられている。その実験であり実践が、精神的なエネルギーを周波数として解剖しようとするパフォーマンス・アートだ。本作は自主レーベルOm Kultからのリリースとも共通するノイズと具体音のコラージュだが、Controlled Death(マゾンナこと山崎マゾのプロジェクト)とのスプリットLPの影響か、ほのかに電子音への傾倒も見せている。
ノースカロライナのenmossedからリリースされた『Imaginary Trip』を聴いた時にも感じたが、Sachi Kobayashiの音響には執着や偏執といった痕跡がない。ハーモニー上の袋小路に陥っていなければ、リズムといった他要素に横跳びすることもない。中だるみせずに直進していく音楽は、制約を取り払うことに自己陶酔せず、呼吸の代わりにつまみをいじるようなストイシズムさえもにおわせない。まるで即席にこしらえたようなシンプルさがあるにもかかわらず、その音響に馴染みが、ない。あまりに滞りなく進んでいくところはAyami SuzukiとLeo Okagawaのライヴとも共通しているが、それにしたって超然としすぎな不在だらけの音楽だ。だが、聴き手が自分で用意してきた物語のための音楽、つまりBGM的な聴取のためだけに作られているとは思えない。
本作の数少ない手がかりと呼べるものは、版元である時の崖のオムニバス『Ultimate_Collection ''hydrocycle on a lake''』参加時の「Chant」と同様に、声、さらに絞るなら声楽が骨子となっている。中盤から添えられるオーロラめいた電子音含め、Organumの教会音楽回帰を連想させるが、あそこまでミニマリズムに接近していない。ああ、結局ないもの探しに終始してしまう。
Cornelius『Point』のようなジャケットで、Cornelius『MellowWaves』のキッチュさを強調したような音楽で、Corneliusのようでない多弁なセルフライナーノーツ(上記URL/QRコード参照)。「突然炎のごとく」の『69/96』的ブルージーギター、『FANTASMA』の1曲目風インスト「denno」の洒落っ気、フランスかぶれの独り言は、未来(の日本の)で拒まれてしまいかねない個人主義的スノビズム=青春。この雑誌内で頻発する「懐かしい」や「デジャヴ」の文字列が筆者にしか見えていない光景に準拠するように、本作を構成するものと取り巻くものの不均衡は阿部某だけのノスタルジアとなって、今もこれからも若さや老成といった語による代替を拒むだろう。優先すべきはこの音楽と世田谷の距離を問うことである。ジャン=リュック・ゴダール『メイド・イン・USA』を眺めていたら、突然日本人女性が出てきて「何が起こるやわからへん」と地でない口調で呟いてしまったことを思い出した。その時のBGMがサティ風エンドロール「鬼火(Le Feu follet)」である。録音とミックスは自宅で行なわれ、それを中村公輔がマスタリング。
ルドルフ・エバーがジョーク・ランツ(Sudden Infant)らと取り組んだパフォーマンス「for amplified brainwaves」は、演者(被験者?)たちの脳波に基づいた波形を増幅させ、演者と観客を八方向から取り囲むスピーカー経由で再生する文字通りのエレクトロニック・ボディ・ミュージックであった。フィールドレコーディングやプラグインのモジュラー・シンセを駆使して新鮮な音響を作り続けるミュージック・コンクレート作家Shuta Hirakiによる『Circadian Rhythms』も、ルドルフが己の脳波に興味を向けたことと均しく、「自身の」肉体から生まれた音楽である。自らの体内時計のズレに起因する睡眠覚醒障害に基づいたサイクル・パターンを設けて倍音や演奏をチューニングしていく方法論は、当事者の内ににしか存在しない個人体験からその理が始まっていることで、ロジックだけでは解体しきれない隔絶の念を音楽に宿す。自己を解体する観察者目線と、切り離すことのできない自分の一部としての肉体を認識する孤独なそれを経過した表現がコロナ禍に出てきた意味は(筆者にとっては)大きい。
New Nostalgic Musicを掲げる宅録作家のEP。音楽を聴いた後にこのコピーを目にした時は、レイ・ハラカミやfishingwithjohnのような音響宅録派を先置いて、筆者が2000年代末の京都のレコード屋各店で目にした自主制作CDたちを思い出したからである。ボソボソしたボーカル、空気としてのエレクトロニカを指向したミックス、ウォーキングではなくブラつきといった具合にヨレ気味なビートがリードするあの京都感、さらにいうなら「左京区感」が、そのつもりはなくとも自分の内側に生きていたことを告げられた気分であった。後からnostola本人が98年生まれかつ熊本を活動拠点にしていたこと、つまり世代的にも環境的にも遠い場からこの音楽を作ったと知った時は、NewNostalgicMusicのコンセプトが一時の懐古主義的なそれではないと実感し、少しだけ嬉しくなったのだった。
あがた森魚のように、nostolaとは深層に蓄積されている感覚を引きずり出すデジャヴ的音楽を作者自身が見つけ出していく旅、というのは仰々しいだろうか。息を殺しながら演奏しているかのような密室シューゲイザー「嘘をついている」と、同じ夕暮れはないことを儚む「放課後」が持つモヤがかったノスタルジアはそんなことを考えさせる。
(22.3/27)