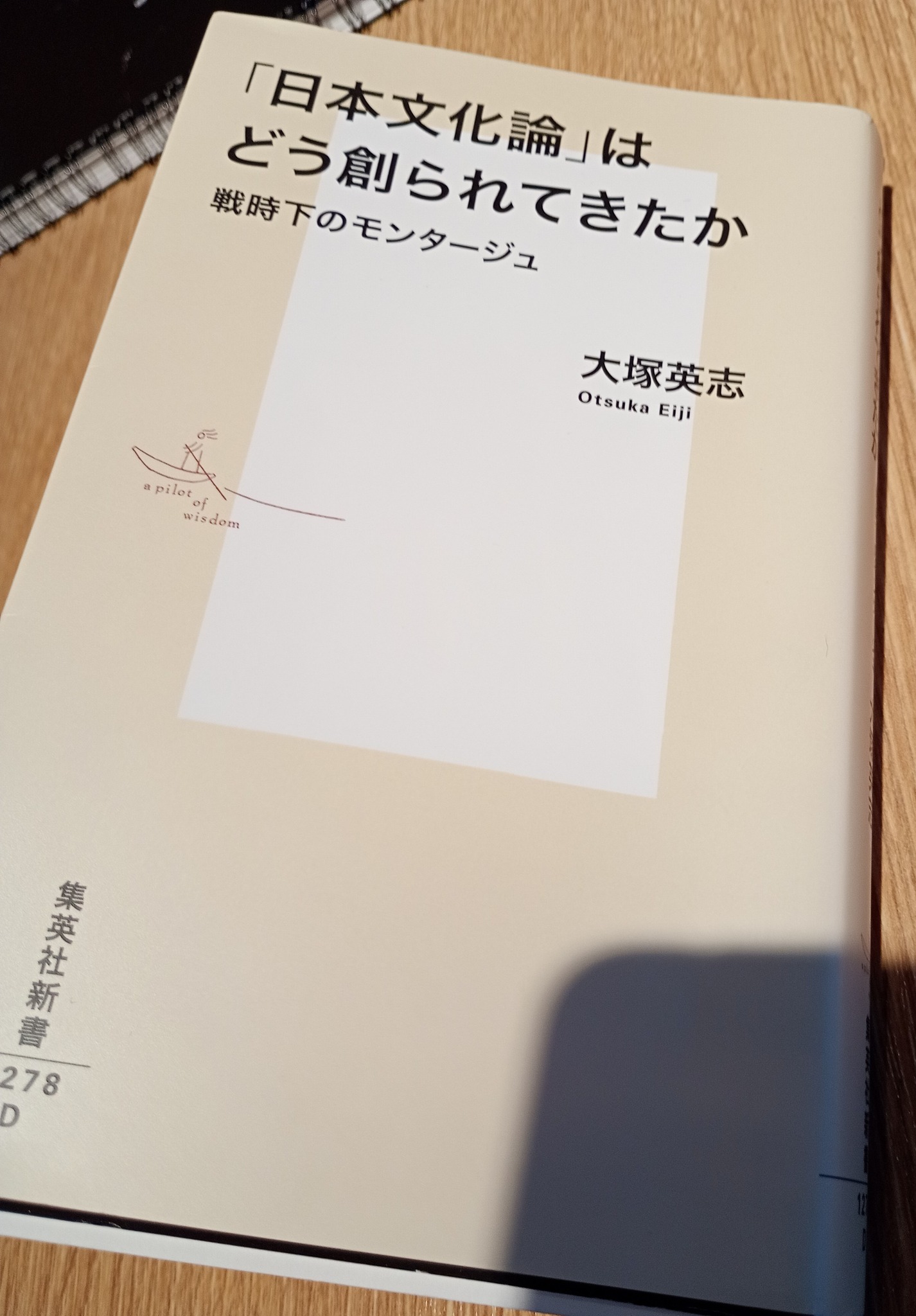
最近読んでいる本であるが、これが一見無関係である今の執筆ごととも接続できる場面が多々あるため、精読にはまだまだ遠い。浅学を自慢してもしかたないが、とにかく例示される事件や人物名自体に疎いので、検索しながら読んでいるし、その作業に充実する。もうちょっと明るい話題だったらいうことないのだが。
ソヴィエト時代の映像作家エイゼンシュテインのモンタージュ理論が、1930年代の日本、絞れば満州国の設置から第二次世界大戦突入・敗戦に至る時期のプロパガンダに影響を与えているという視点からはじまり、ナショナリズムが文化に水やりしていく過程をたどる。それは必要が発明の父母ともいえる力学で、大衆的な必要性が薄い芸術の分野にこそその尽力具合がすさまじかったことを教えてくれる。いや、現在と比較させてくれるというべきか。戦時下のプロパガンダによって蘇生させられた日本のフォークロア(失われつつある伝統を守ろう的な)、あるいは国威発揚的な意味合いを与えられた「報道」(道が導に置き換えられる)や「日常」ということばは、政権がアレで、それに忖度するアレらがいて、小泉八雲を主人公にしたドラマが放映されているいま・ここと重なっている。そんな時期に出ただけでもこの本の価値は疑いようもないが、80年前を再訪するはずが現在を見せられている感覚は、いま・ここで読んでいる人間だけが感じられるものである。
エイゼンシュテインは『戦艦ポチョムキン』はじめとした映像作品が多数サンプルとして出されており、スクリーンショット一つだけでも、一つの画に異なる時間を持った絵を挿入するモンタージュを視認できる。万博のために輸出を念頭に置いて作られたイメージ、外国にも伝わるように言語ではなく視覚で訴えることを重視したそれは、エイゼンシュテインのモンター
ジュという具体の切り貼り的提示の方法がとられている。終章の手塚治虫への論考=マンガへのリファレンスが強調されるように、一つの事物をバラバラに区切
り、コマ的に並べることで静止画が時間の概念を得るという作り方が、いかに情報ないし情緒を与えるかが分析される。
しかし重要なのは、エイゼンシュテインの提唱したモンタージュ「論」」であり、それが流用されて自国のプロパガンダへと発展していく過程だ。レニ・リーフェンシュタールによるナチスドイツ喧伝写真が、体操の紹介記事内でデカデカと紙面を覆う写真、運動を捉えたそれへと政治的コンテキストが継承される。それを10代半ばの三島由紀夫少年が詩で察知していた事実含めて、戦争が空気としてあった時代が描かれる。不気味なのは、自分で生きておきながら、いま・ここでこれに類する出来事があるとわかりつつ、それを実感しにくいところにある。いや、正確にはどう反応していいかがわかっていないのではないか、自分は?
潔白は滅ぼされることでしか表現できないとは考えたくないが、それまでの心中は記録しておくに限る。手塚治虫が進行する世界をマンガとしてパッケージして、今日まで残してきた事実は、当人にどれだけの意識があろうとなかろうと関係のない大ごとである。マンガの方法論の進化が美的かつ論理的、現実と孤絶された時間軸で行なわれてきたというのはやはり無理な考え方であり、何をしたかを問うことが批評の役割であると月並みながら考え直した。考え直した、とは世間(戦争含む)から離れた生き方をせんとする自分を省みる意味であり、改めたわけではない。たとえば高市政権でなければなんでもいい、という理屈にはなりえないのであって。あらゆる結果は、遡及されてこそである。
(26.1/23)