メモ・9枚のアルバム+αを挙げて、謎
私を構成する9枚と謎
Twitterで「私を構成する9枚」という趣旨でアルバムを挙げる流れがあったので、便乗して色々挙げてみた。「構成する」って・・・ナニ?と思いつつ、要は思い入れのあるものを挙げろということだろうと判断して、色々選んでみたのだが、実に懐古的な内容となった。日ごとに変わるようなものなので、特に大袈裟な意味はないが改めてここに記す。オマケに何枚か追加で挙げている。結局、『スーパードンキーコング』と『MOTHER2』が一番や、という結論にならなかっただけマシか。カーソルを載せると作品名とアーティスト名が、クリックすると詳細へと飛びます。
 |
Nurse with Woundはじめとしたファミリーたちは音楽嗜好を決定づけた点で重要なのだが、いかんせん数が多く、しかも似たり寄ったりのものもあるため、選ぶのが難しい。無難に最初に聴いた本作をチョイスした。これは82年に出た名作で、このジャケットは92年の再発CDにのみ使われている。一聴して気に入るような作品ではないのだが、このアートワークとサウンドが不気味なほどにマッチしていて驚いたのは確かだ。今振り返れば、フリージャズ的だったコラージュが、きちんとした構成で組み上げられるようになった転換点と言える作品。「シュミュルツ」は20分以上の大曲だが、再生が終わるまでずっと耳を澄ましていた最初の体験だったと思う。再発版全てに1曲追加されているのだけど、このCDだけ次の曲にシームレスで繋がるミックスになっており、微妙ながら、こちらに思い入れあり。 |
 |
Current 93の90年代を代表する一作。恐らく何十年後に聴いても古いとか新しいといた基準を無視するであろう、由緒正しきトラッド・ソングが完成した頃の作品は時が経つほど美しく響く。子守歌が子供に与えるイメージは安らぎから恐怖まで横断するものだ。そして、時代や国を問わず、子供はその空想を自分の中に育んでいる。おとぎ話を音楽にした、なんて例えは弾に見るけれど、これにこそ贈られるべきだね。アシッド・フォークと実験音楽が出会うことで生まれたアポカリプティック・フォーク最高の例の一つだろう。「ザ・ブラッドベルズ・チャイム」は彼らの曲の中でもベスト5に入る名作。 |
 |
実質ラストアルバムとなったCoilの名作だが、当時はどれくらい話題になったのだろうか。高騰していて入手困難な彼らの作品は時系列バラバラで聴いてきたが、半ば暗示のように再生を重ねないと好きになれない世界で、一聴して打ちひしがれるような感動を得たのは後にも先にもこれだけなんじゃないかとすら思う。ジョン・バランスが亡くなった事実もあり、キャリアの中でも抜きんでて特別な位置にある作品だが、前作『ブラック・アントラーズ』から更に進歩しているのは明白。それまではエレクトロニカやIDMといったマニア向けの棚に入れられるような敷居の高さがあったけど、これは多くの人に聴いてほしいと思える作品だ。バランスの歌もあって、立派な英国流のポップスになっていると、改めて思う。ラストの「ゴーイング・アップ」は日本人にはちょっと作れない。 |
 |
電グルは砂原派なので、ソロも氏のものをたくさん聴いた。デザインとして音楽に着手する氏の考え方も好きなので、この架空の空港とフライトを描いた大作も、コンセプトからアートワーク込みで気に入っている。内容はハードハウス、ラウンジ、スペースミュージック、オールディーズと、90年代に隆盛する"モンド"の決定版。自分がサウンドトラック好きになった一因は間違いなく本作の影響がある。アートワークと再生回数自体は次の『The Sound Of 70'S』の方が上回っているけども、ここまで綺麗にまとまっている本作があったからこそ、次に繋がったのだろう。自分にとっての90年代のイメージの一部が、このレトロフューチャーの復刻によって築かれたのもなんだか感慨深い。 |
 |
セガのゲーム『ROOMMANIA#203』の中に登場するという設定のセラニポージだが、実際にCDもリリースされた。ゲーム内で聴ける楽曲を収録しており、ヴァーチャルアイドル的な触れ込みを割と早い時期にやっていたことになるのだろうか。とにかくゲームとセットで愛聴していた作品で、ド田舎在住の自分はゲームと世良にのおかげでレディーメイドや渋谷系といった世界を知ることができたのだ。作曲はゲームのアイデアを生んだササキトモコ(逆さ戦メリでも知られる)、プロデュースは福富幸広、デザインはGROOVISIONと田舎の小学生には勿体ないほどの洗練ぶりだが、そんなカルチャーとぶつかるきっかけが得られるだけ自分はラッキーだったのだと思う。好きを通り越して感謝すらしている作品だ。ハウス、シャンソン風など、ウィスパーボイスを活かすアイデアがあちこちで実践されており、今聴くとその引き出しの多さに驚く。 |
 |
最近になって認知され始めたような気もするスクービーだが、彼らのアイコンとなるスーツ、アレンジへの拘り、赤面モノの歌詞が押し寄せてきた名作。テレビやラジオのコマーシャルで流れてきてはすぐに忘れてしまう無責任な文句に辟易する一方で、それに近いというか、もはやそのものを歌っている彼らを長く支持しているのは、最初こそ「中身はともかく曲がいいから」なんて恥ずかしい理由だったが、今では筋を通すために取り組み続けるその根性または狂気と言っても良い開き直りに敬服すらしているから。日々崖っぷちな自主経営もあって、「でも、やるんだよ!」を地で行っております。楽曲は現在でも健在のイントロ殺しが詰め込まれており、1曲から4曲目までの怒涛の流れは夏のようにあっけなく、何度でも嬉しくさせてくれる。 |
 |
嫋やかで贅肉を削ぎ落したサウンドに破綻した歌詞が延々と乗り続ける様に衝撃を受けた作品。話すように、加えれば井上陽水のようにそれを呟き続ける山本精一と、抑揚のないボーカルを吐き続けるPhewは対になっているようで、そうでない。「まさおの夢」は全く理解できないが、だからこそ歌と言葉の価値がわかる。アシッド・フォークやサイケなど、例えは出来るだろうけども、ここまで孤立した世界もないため、最初に聴いた頃は人と共有するようなものではない気がしたし、今でも、少しそう思っている。 |
 |
ファクトリーではJD(New Order)よりもドゥルッティ派なのだが、その理由は前者をはじめとした多くのポストパンク・バンドがギター、ベース、ドラムからなる普遍的な編成で、個々の違いが正直よくわからなかった時期にこの嫋やかなギターとリズムボックスだけで構成される詩編を耳にしたからだと思う。叙情的なメロディはとてもパンクなんて名乗らないように聞こえるのだが、触れるものを傷つける紙やすりスリーヴ伝説にはじまるファクトリーのアイデアや、レーベルと創立者を失った今もなお、反ビジネスというポリシーを出来る限り続けるヴィニ・ライリーはオリジナルのパンク以上にそれらしい。アートワークとサウンドが一致している作り手は、と尋ねられたらとして真っ先に挙げたいのがドゥルッティだ。 |
 |
匿名とマルチメディア、この時期のルックスなど、表層的な部分で関心のあったレジデンツだが、重要なのは彼らが本流に対する亜流ではなく、自分たちで新しい本流になろうとしたことだと思う。彼らに励まされた人々の多くは、本流についていけなかったり、そこに入らねば生きていけないような風潮が気に入らなかったりするのだが、レジデンツは逃避しながらも世間へ攻めることに成功していたからお手本となっていたのだろう。特にアイボール・マスクの頃は最盛期で、本作はラジオ番組の時間帯を買い取って、自分たちの曲しか流さない枠を作るといった、資本主義を操縦するコンセプトと、楽曲の完成度が見事に噛み合っている。一般性があるけど、よくよく見たら毒とテーゼがある。「Amber」とラストの「When We Wer Young」が泣けます。 |
以下の3枚は最後の3枚と入れ替える可能性あり、くらいのものである。
 |
『THEビッグオー』はサンライズ制作のアニメで、自分の60'sとサンプリング好きを育んだ重要な作品である。ディティールが素晴らしく、ロボットアニメじゃなくていいじゃんというツッコミを毎回してしまう1stシーズンの劇判は佐橋俊彦による珠玉のモンド・リバイバル。対象が遠い時代故に、ノスタルジーとはまた異なる憧憬を与えてくれる作品だ。主題歌はお蔵入りになってしまったクィーンのパロディ、Uボート、トワイライトゾーンといった往年の作品の断片が次々に現れては、自分の剽窃狂いを加速させる。エンディングの「星に願いを」風バラードも素晴らしい。高騰しているのだけが本当に惜しまれる名作だ。アニメも(1stシーズンだけでもいいから)見てください。 |
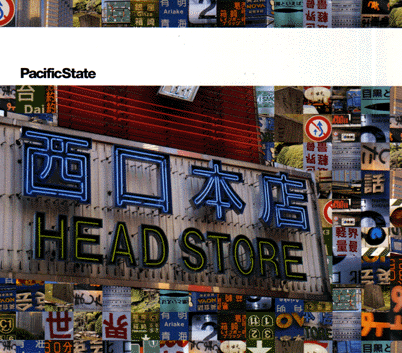 |
ソニーが出したテクノのコンピレーション。当時の勢いが伺えるもので、2枚組ですべて日本人アーティスト、オール書き下ろしという豪華ぶり。また、テクノの定義が今よりも曖昧だったので、DJ KRUSHやダズルTといった、微妙に離れたクラブミュージックの雄たちも登場している。今となっては簡素で渋いモノばかりに聴こえるかもしれないが、最低限のボリュームでイメージを育むのがテクノだと自分は受け取った。ジャケットは正直時代を感じるが、確かに90年代後半は東京がテクノの発信地であり、微妙に異なる世界の面々が同じ船に乗っていたのだ。まだ30年も経っていない世界だが、テクノに歴史あり。音楽よりもその時代が好きなのかもしれない。誤訳をわざわざ訂正した日本語ライナーもヴィジュアル込みで見ものです。 |
 |
ハーモニーを知り、意識したのはクィーンだった。コイルのような音楽を聴いた時も、最初に思い浮かんだのはクィーンだった。植松伸夫のサウンドトラックもELPと並んで比較対象に挙げたクィーン。西洋音楽でいう、「美しい」の基準となったバンドとして、自分の中で奇妙な立ち位置に居続けている。アルバムは正直、通して聴けるほど良いと思ったことがないため、このベストヒッツを楽しんでいるのだが、否が応にも高揚させるマジックの数々に日々泣き笑い。ボゥイと書いた永遠の名作「アンダー・プレッシャー」、つられて歌いたくなる「キラー・クィーン」、「ザ・ショー・マスト・ゴー・オン」による幕引きは圧巻だ。 |
戻る~にゃ








