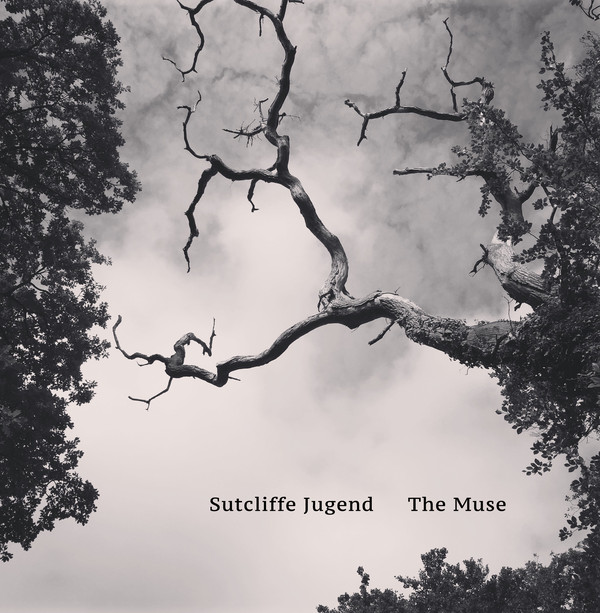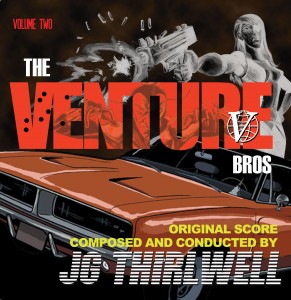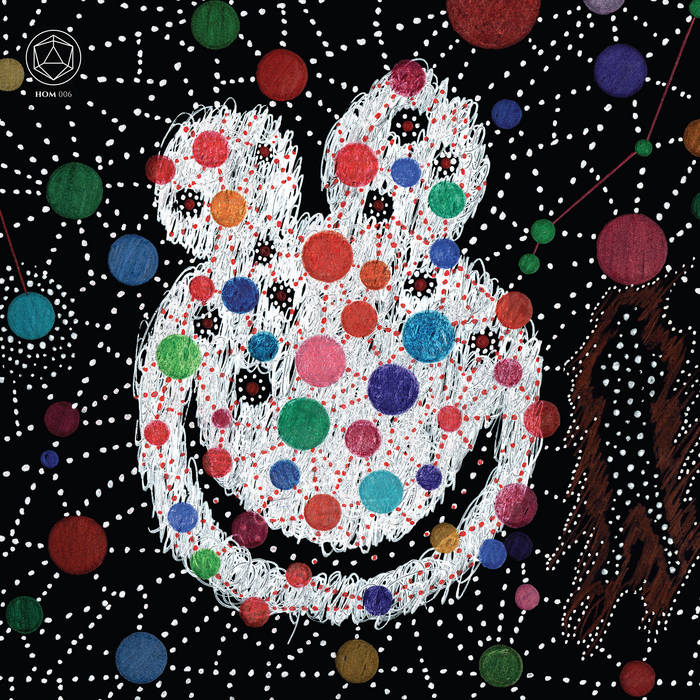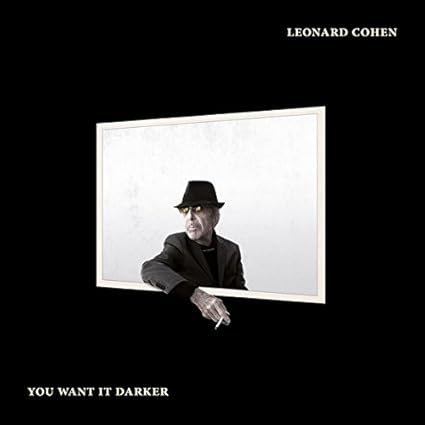今年も聴いたものから、特に良かったものをまとめてみた。順位付けは正直意味がないとわかったので下に行くほど良い程度である。
11月から書いていたものが多く、一部は海外のWEBマガジンに提出して校正中であったり、送る予定だけがある。実際に受け取られるかは不安である。
英語への翻訳が拙すぎるのもあってスムーズには発表できないと思うが、公開された際は何卒...。ああ、もっと勉強しておけばよかった。
今年はApple Musicなどでずさんに聴いては忘れる例が目立った。身の丈に合う出会いを大事にしたい。一部は画像クリックで購入先へ飛ぶ。それが大事だ。

|
ショーン・レノンとレス・クレイプール(プライマス)によるユニットという出自からして驚く作品。レノン、つまりビートルズの子供と、彼らの正統後継者たる奇形児レジデンツの(精神的な)子供が手を組んだと言えばいいか。歌詞もサウンドも完全に60's西海岸発レジデンツ経由のサイケデリック、一瞬だけザッパと連結するような遍路である。演奏が古臭いだの、先駆者への愛がないなど、『サージェント・ペパーズ』をロック・アルバムとして評価するくらいに無意味な試みはしちゃいけないよ。メディアに取り上げられて褒められることで、ビートルズもザッパも同じ売れ方だったことを再び証明し、更に両者の子供であるレジデンツによるサイケデリックの製図を引き継いだことが重要だ。マイケル・ジャクソンのペットを歌う「バブルス・バースト」は後者の顕著な例で、ガーシュイン、プレスリー、JBら米国の伝説と生贄を歌ってきたレジデンツもそれほど踏み込まなかったネバーランドに標識を立てた。
明解米国音楽史(by『踊る目玉に見る目玉』)もといサイケデリックの歴史を紡ぐ、世代を超えた近親相姦。同時に来年3月のレジデンツの来日、異母兄弟であるレナルド・アンド・ザ・ローフによる30年ぶりのアルバムの報せを知った年末になって気付いた、一族逆襲の狼煙でもある。
|

|
brainwashedの広告スペースに表示されていたことで知ったクラウドランド・キャニオンの新作。LCDサウンド・システムにも参加していたドラマーが一時期加わっていたこともあり、00年代のウェルメイドプレイなロックバンドの一つになれたはずだったが、一部のクラウトロックやディスコが持つ「コズミック」の概念にこだわり過ぎて、マニア向けの世界に行ってしまって、そこが好きだ。本人らの声を聞くまでもなく、ノイ!や「C」のクラスターといったクラウトロックのフォロワーだと丸わかりだが、2000年結成という出自は伊達ではなく、90年代に浴びた洗礼、例えばシューゲイザーからも逃げられませんと音で告白している。
影響元の一つであるはずのティム・ゲインが今年出したアルバムとの違いもそこにあるような気がして、参考と結果にそれほど距離がない様相は、あくまで自分たちが育った時代に居座り続けると拘った(と同時に未練がましい)成果なのだと思う。
ハンマービートはもちろん、ちゃっかり採用している00'sエレクトロなベース、ウィスパーボイス、オマケにヴォコーダーといった各ジャンルの特徴を積み重ねた節操のなさが、円熟したゲインたちの新作よりもカッコよく響いた。再生時間も短めというのも個人的にありがたかった。 |

|
進歩の仕方は人それぞれだが、そんなエクスキューズを挟む必要も余地もないのがヒロシ・ワタナベの新作。世で繰り返される原点回帰とか新境地なんて形容も入り込めない振り幅の少なさを持つテクノを切り続けて幾年、トランスマットから出すとなっても、その佇まいは変わらない。遡ればフロッグマンからのリリース、クラブ・ミュージックへの関心を断片的に見せていた『ビートマニア』での職人仕事、そしてコンパクト期からkaito名義に連なる作品と、これらがそうだったようにキャリアのすべてと今作がしっかりと一本の線で繋がっている。何を咀嚼しても、何を使うとしても同じ到達点を目指す姿に孤独すら感じるが、同時にそれを楽しんでいるようにも見える。仏像彫りにも近い境地は、ストイックも突き詰めれば我儘となる証左。
|
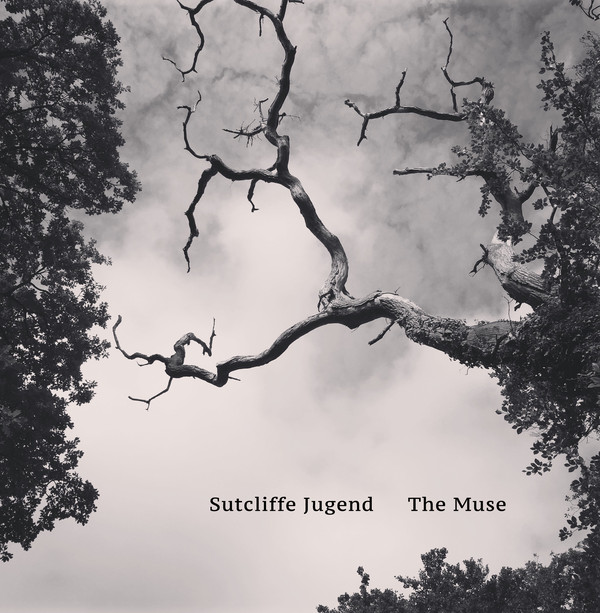
Sutcliffe Jugend
The Muse |
サトクリフ・ユーゲントの新作で、今年はパワーエレクトロニクスと呼ぶにふさわしい『オファル』など、いくつも新作を出している。リリース元の窓口がないせいか、発売したことすら知られていないのかな。Discogs経由で買いました。
『オファル』と対称的に、ダウナーなドローンとノイズに終始する内省的なサウンドだが、二つを比べてみれば永続的なドローンをバックにブツブツ呟くのも、瞬発的なハーシュと共に叫ぶのも、共通したメッセージとバックボーンから出ていることがわかる。要は言葉とそれを乗せる器は別個であることを宣言しているわけである。ケヴィン・トムキンスの古巣だったホワイトハウスだって、今はトライバルなグルーヴで圧倒するカット・ハンズになっている。使い古されたスタイルを見限るか、測量の道具として使い続けるかは個人によるが、『ザ・ミューズ』がハーシュを用いないことで、逆説的にそれを未だに使用する理由を証明しているのも確かだ。また、ハーシュだろうがアンビエントだろうが、この退廃した世界は英国の空気なしでは生まれ得ない。そんな彼らのポリシーとお国柄が強調されたリリースであった。 |

|
オーレン・アンバーチがアート・リンゼイやジム・オルーク、マーク・フェル(SND)、リカルド・ヴィラロボスなどの面々を招いて作ったジャム・セッション的な一枚。何をしてもボリュームのある作品になりそうな陣営なのだが、ケルン~デュッセルドルフあたりの西側クラウトロック的な着地を見せていて面白かった。一曲目はカンの『フューチャー・デイズ』、3曲目はメビウス、マニ、プランクによる『ゼロ・セット』まんまで、後者はリンゼイのギターがあちらにない良い味を出している。この辺は独以外だとマサカーあたりが好きな人にピッタリ。個々の音自体はそれほど上述のバンドをモデルにしたという感じはせず、あくまで統合した結果であり、アンバーチのアンテナがどんな風にチューニングされているかを示すような作品だ。
例えをクラウトロックだけに絞るのも短絡的だが、やろうと思えば3曲目を 『E2-E4』ばりのミニマルにできたのかもしれない。それともラ・ノイ!が日本公演でやった90分に及ぶ「チャチャ2000」のように人力で演奏し続ける方が今回のスタイルの完成系だったら、どうだろう。今回だけの企画だとしたら勿体ない。 |

|
マルコ・ド・マルコとジョバンニ・レオ・レオナルディを中心にしたプロジェクトだそうで、本作のために結成したのだという。バンドを背にした演劇と言えば早いか、ニコがいた時のヴェルヴェッツにも近い。実際に最後の曲は「アイル・ビー・ユア・ミラー」のカバーである。音楽や映画の果てにオペラがあるという認識は珍しいものではないが、あくまでこれはアルバムの範疇でそれに近づこうとしている。「ジャリコ」はエレクトロニクスをふんだんに使ったもので、自分の嗜好ならばカレント93やフィータスの世界にも通じているため、すんなり聴けた。声明的なネタを使った曲もあり、ユニバーサルな内容だ。「イヌティ・オジャッティ」は一転してロックとなり、個々の演目の違いがハッキリして面白い。ソル・インヴィクタスやタイガー・リリーなどヨーロッパに根を張るダーク・キャバレーのシーンを意識しているかは判断できないが、脈々と続く演劇とロックの関係、ニコによって頂点を迎えていたそれはひっそりとだが、受け継がれている。言語に疎いのが惜しいけれど、ヴェルヴェッツのカバーが染みるのはそのおかげでもある。イーノがカバーした「アイム・セット・フリー」と共に。
|

Nick Cave & the Bad Seeds
Skeleton Tree |
音のプロデュースと作曲はケイヴに加えて、過去に劇判などをいくつか共作していたウォーレン・アリスということもあり、流行り廃りの軸から離れた不易のスコアとなっているのは変わらずだが、息子の死、加齢、世相の変遷などなど、幾つもある因果が重なり合ったこその本作であるのは明白か。多くが抑揚のない曲だが、後半に突如流れるバラードにケイヴの本音とすがりたくなる希望が表れているよう。闇一色のジャケット上に浮かぶフォントが瞬くかのように明滅する歌が素晴らしく、レナード・コーエンのように暗くとも澱みのない作品だ。 ぼんやりと浮かび続ける灯火のような佇まいに、こちらから歩みを寄せてしまう魅力を有している。世界を切り取って俯瞰するアノーニとの違いは個人の世界に没入していることだが、触れてくる感情はあちらとも共通する普遍的なもののはず。それを悲哀や悔恨と表現するのは正しくない気がするが、ふさわしいものも思い浮かばず。
|

|
ジャケットが面白かったから買ってみたサラミ・ローズ・ジョー・ルイス。LAを拠点にしていることしか知らないのだけど、あんな暑い土地でこのジャケットというのだから人を食っている。チープな電子音とウィスパーボイスが繰り返される短いシャンソン集で、こう書くとブロードキャストやコンピューター・マジックっぽいと思われそうだが、ちょっと違う。レパートリーの少なさも「キャプテンb.ハート・エスケイプス・イントゥ・ザ・ナイト」なんて曲名を見れば納得してしまうように、60年代後半の西海岸サイケデリックが見せていた逸脱を感じ取ることができる。毒でもなし侘しさでもなし、キャピタル時代のビーチ・ボーイズっぽさもあり。ワープやキツネから出るとは思えず、bandcampで出ているのがピッタリの孤独がまた愛らしい。近い印象を受けるのはゲームだけど『MOTHER2』かな。「tell meeee」や、「hukie wookie」で泣けてきて泣けてきて...ラヴの3rdアルバムA面みたいに泣けます。 |

|
前作同様、日本の民謡や音頭を素材に作り上げたキメラ的ポップスの続編。より洗練された素材の料理は、出オチの飛び道具になりがちなモロ使いとは一線を画す。和風を取り入れたで終わらせたくない咀嚼ぶりは、外国人だからこそ持てるフラットな視点故か。和洋折衷とはモーマスが崇めるボウイも軽くいなしたテーマの一つだが、本作ではもう一人のアイコン、ハワード・ディボート流のシニカルかつ悪趣味すぎる歌詞がより強く歌を支えている。録音中に英国がEU離脱なんてしたもんだから、 Macbookを媒介にグローバリズムを語るなんてラインが控えめに感じるほどに強い執着が向けられては、前作よりもずっと手厳しい皮肉が詰め込まれる結果になった。ネタの素材と直接的すぎる歌詞で敷居が高いように感じるかもしれないが、そこはエルやクリエイションから出していたこともある御仁だけに安心して良い。爽やかだけど気持ち悪い、そんな矛盾からもポップスが生まれることを何度も証明してきた奇才の舞踊。 |
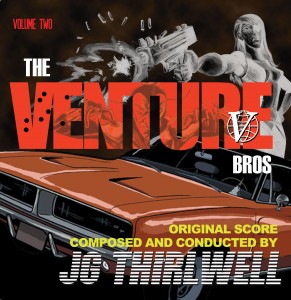
|
JG Thirlwellが劇判を手掛ける米国産アニメ『ザ・ヴェンチャー・ブラザーズ』のサウンドトラック第2弾である。曲自体は09年から13年ごろに書かれたものが主であるから、完全な新作とは言いにくい。でも、それ以前に今回のリリースがなかったんだから仕方ない。『ヴェンチャー』がモデルにしている『ジョニー・クエスト』といったカートゥーン、日本のものでは『カウボーイ・ビバップ』に顕著なビッグバンド・サウンドに加えて、今回はスペースオペラの成分が強めである。ステロイド・マキシマスといったプロジェクトはもちろんのこと、フィータス名義だって80年代の時点からスパイ映画、モンド・ムーヴィー、SFのサントラを吸収していたが、『ヴェンチャー』があってこそ、コンポーザーとしての成熟が果たせたのは明白。交響楽からビッグバンド、シンセサイザーを介してのミニマル・ミュージックまで達する引き出しの多さと、それらの融合はサールウェルの才覚をこれ以上ないほどに紹介している。「チキンホーク」や「プラックト」なんかはこの人にしか作れないでしょう。
「ハム・アンド・チーズ・ヒーロー」は間違いなく今年一番聴いた曲だ。日本は無視しているがシーズン6まであるよ。 |

Shirley Collins
Lodestar |
38年ぶりに出したアルバムだそうだが、カレント93を通して知った時にはレジェンドという枠からも既に外れている存在だったので、過去の功績と比較なんて出来るわけもなかった。カレントと彼らが紡いだ詩と音楽こそコリンズへの唯一の手掛かりだったので、そんな耳をもって聴いてしまうのだが、そのおかげでザ・ブルー・エアロプレインズのイアン・キーリーとサイクロブ(!!)がプロデュースという出自が既にアポカリプティック・フォークの規範に忠実だと感じる。トラッド・ソングと実験音楽の融合が、チベットの理想そのものであったコリンズを介して作られることで、改めて英国トラッド史上の二点が一本の線で繋がったわけである。バックはわずかなリフレインが主で(音が良すぎる!!)、齢80を超えた声の魅力を引き出すように作られた渋さも聞き逃せない。オシアン・ブラウン(サイクロブ)によるハーディ・ガーディとミヒャエル・ヨークによるスモールパイプのハーモニーは、正しく彼らがサポートに入っていた後期コイルのそれと一致するもので、今年に『ジ・エイプ・オブ・ネイプルズ』が復刻されたこともあって運命的に感じた。姉のドリー(95年に死去)と書いた曲の再録からも察せるように、曲は書いて、弾いて、歌うだけではなく、残していくものであるという気概が純朴な音に包まれている姿が何より美しい作品だ。
|

The Hardy Tree
Through Passages of Time |
フランシス・キャッスルという方のプロジェクトで、本業はイラストレーター・絵本作家のようだ。もちろん、このアートワークも自前のものである。音楽のクオリティは相当のもので、とても片手間でやっているようなものではない。
なんとなく、ドゥルッティ・コラム、それもクレプスキュールに出入りした時期のそれを思い出す。全編インスト・ナンバーで、ムーグやメロトロンの音色を筆頭に80年代よりも前の時代らしくしているのは、かつて存在したロンドンの建物群をイメージしたというコンセプトゆえか。ここで描かれる追憶は、今年のEU離脱といった時勢から生じた後悔と同義のものというよりは、もっと以前から抱いていた郷愁、生まれる前の時代から受け取っちたそれに近いと思う。ある意味で架空のサウンドトラックだが、それは空想として描いた風景ではなく、確かに存在した土地と時間についてだ。だからこそ、昨今の出来事を印象付けるのかもしれない。日本よりもはるかに歴史があるヨーロッパだからこそ、失われたものへの回顧にリアリティが宿るのだろう。離れているとはいえベルリンを見てきた年に聴けたから、上のような感想を抱けたのかもしれない。そんな縁と思い込みをちらつかせた不思議な作品であった。聴いてるだけで楽しめるのはもちろんだけど、ここはイラストレーションと共に鑑賞したくなるのが道理である。こちらから。 |

|
これまでのチェンバーな編成から一転して、OPNことダニエル・ロパティンとハドソン・モホークを起用したエレクトロニック・サウンドに歌を乗せた意欲作。詩は多対一の世界でありつつ、普遍的な一対一と同義であり、至近距離で見つめられるような険しさと痛々しさを併せ持つ。ジョンソンズやカレント93では出来ない所業で、数少ない類似例は過去に出たライヴ盤『カット・ザ・ワールド』に入っていたスピーチかな。
詩で語られているのはあらゆるマイノリティとそれを圧迫するもの、そして二者を立証することを無意識に拒む第三者たちで、「ドローン・ボム・ミー」と「4ディグリーズ」のように複数の視点を介して、一つの現実を炙り出す。
歌詞に対して煌びやかなサウンドは糖衣のようでもあり、それが本作をマーダーバラッドに仕立て上げている。
カレント93がトラッド・フォークから見出した境地と共振するところは多分にあるだろう。この手のサウンドが将来的にトラッド・ソングとなり得るかはわからないが、完成した時点で本作は過去となり、重要なのは次である。
|

David Bowie
★ |
どことなく『ロウ』にも通じる退廃的な世界観が、同作にはなかったダイナミックな演奏によって昇華した作品。大輪の花を咲かせた新しいジャズを取り込み、静止したまま世界の目を引き寄せるボウイの儀または歌舞伎を果たした意欲作であると称えるのが、セッションした新鋭と称される面々にも誠実なのだろう。が、どうしても今まで想像で埋め合わせていた死への実践が、このアルバムの録音から発表、その二日後に至るまでの道筋だという方向に引っ張られてしまうのは無理もない話。しかし、事実が真実であるとは限らない。それどころか、ボウイの歩みや、咀嚼してきた文学や宗教、神秘主義、タイトル曲でも使われたモチーフを含むオカルティズム、そして自身の死とその前後の時間だって、人の生き方に真理がないことを示す例なのではないかとも思う。それは最後の曲名及びラインにも表されているはず。発売して暫くはマクドナルドで「ラザロ」が流れていたのも、思い返すと凄い。
|

Michael Arthur Holloway
Guilt Noir |
『Music Of The Venture Bros Two』と並んで、1年通して聴いた作品。50,60年代をモデルにしていることでも共通しており、こちらは半世紀前のニューヨークを描いたノアール・ジャズ。ロバート・グラスパーのようなジャズ最前線と合流しているわけではないのでご注意を。ここに収められているのはサウンドトラックのアイデンティティに忠実な、コンセプトを根拠立てるための曲だ。ミヒャエル氏のバックボーン、曲を紡ぐ技術やメッセージの媒介など、外へ主張することを前提とした音楽よりもずっと奥手で、夢想の中に沈んでいく逃避的なそれである。まさしく映画を鑑賞している時の目線に限りなく近いもので、流行はおろか、現実すらも無視しているような作品だ。そのことから、嗜好品の枠を出ていないだとか、内省的どころか独善的と受け止められても無理はない。雨の夜、一人で歩く橋の上、『ツインピークス』がもし50年代に録られていたら。ここまで強力なイメージを並べてしまえば、この着地は当たり前かもしれない。しかし、それを今の時代に選ぶ弱さと酔狂、何よりこれらを貫いてアルバムを作ってしまった頑固さに励まされるのも事実なわけで...。「ショート・チェンジ」だけでも聴いてみて。
|
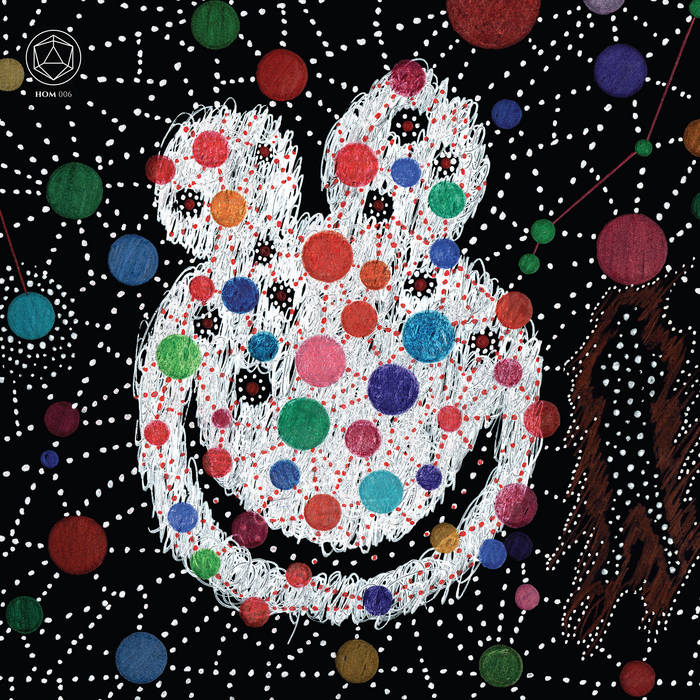
Hypnopazūzu
Create Christ, Sailor Boy |
カレント93のデヴィット・チベットがユースと結成したプロジェクト、ヒプノパズズのデビュー作。ジ・オーブの新作にもプロデュースで参加しているユースなので、キリング・ジョークの元メンバーという紹介は流石にふさわしくない。
近年のカレント93はアノーニやコーマス、ジョン・ゾーンまで引っ張り出すスーパーグループで、チベットはさながらジョン・ケイル、またはコックニー・レベルと肩を並べるような佇まい。かたや、ユースのソロはかねてから関心のある東洋思想を骨組にしたニューエイジ路線なので、ヒプノパズズは音から声までラーガ的な内容になるだろうと勝手に思っていた。が、実際に曲を聴いてみれば音源ではご無沙汰だったチベットの熱唱に、分厚くダブっぽいベースライン、更にはポポル・ヴーのサンプリングという変化球に至るユースのディレクションが合わせ技となるゴージャスな内容に驚く。自身らの音楽へ反映させる機会こそなかったけれど、両者が前々から寵愛していたプログレッシヴ・ロックはもちろんのこと、ジューダス・プリーストやクィーンに至る絢爛さへの追及が眩しすぎる。ロブ・ハルフォード、じゃなくて、ロック・シンガーとしてのデヴィット・チベットが克明に照らされた感動的な作品。
|

Matt Elliott
The Calm Before |
サード・アイ・ファウンデイションとしても知られているマット・エリオットだが、本名名義によるダーク・フォークシリーズにこそ氏の真髄があるのは『ソング』三部作でも証明済。ヨーロッパでないと生まれ得ない、曇天時々荒天の下を表したような曲は、穏やかに進みつつも、時に荒波のような怒涛の展開を見せる。エストニア出身の彼の母親が辿った逃げ場のない日々と、それを亡命者同士で共有できた教会、そこで歌われていた聖歌がインスピレーションになったらしいが、東欧の音楽から影響を受けつつも殆どの曲を即興で作ったとのこと。アコギを使う上では逃げられない叙情的なテイストも、墓前での独白のような呟きが乗れば、喪失とその余韻に浸るかのような一時を生む。そんな不毛で孤独な時間が愛おしい。
本格的に楽理を学べば、より素晴らしい作品が生まれることは容易に想像できるが、本作がそうした洗練から生まれない類の記録であることもまた真なり。今年はニック・ケイヴやレナード・コーエンのような、歌が自分そのものになってしまう程に繊細な作品をよく聴いた。これはその先駆けだったと思う。かつてヤエル・ナイムらとコイルへ捧げた『This Immortal Coil』と共に。
|

テニスコーツ
Music Exists Disc 4
|
今年出たdisc3の感動も収まらぬうちに出されたシリーズ完結作。今までマスタリングを担当していた宇都宮泰氏が録音から参加、音は加工される前の段階で数多の実験を施されている。氏が過去に手掛けてきたアフター・ディナーやジョン(犬)と同様に、録音は最も創造的なプロセスだと言わんばかりで、音の鳴りを追いかけるだけでそれがわかるだろう。実験がポップスとして結実するという着地は歴史も証明していることだが、ここまで長閑で遥かな歌に帰結するのは出来過ぎてて、美しすぎる。もちろん、それに耐えうる曲があってこその話で、テニスコーツの最新がいつも最高である所以でもある。曲のアイデアはこれまでのシリーズと比べてユニークで、3拍子ミニマル「サンマ」、度肝を抜く歌唱「似たものどうし」、珍しく直接的なテーマとハッキリした展開を持つ「渡り鳥」(鈴木卓爾監督『ジョギング渡り鳥』から引用しているそうで、近々観てみたい)など、disc3より曲数が少ないながら、表情の豊かさはこちらの方が上。容易に比べられるわけもないが、これまでで最もシンプルな詩も含め、こちらをベストとしたい。似たような感覚はPhew&山本精一『幸福のすみか』を最初に聴いた時にも抱いたような...。ジャケットも素晴らしく、アナログで欲しいです。
|
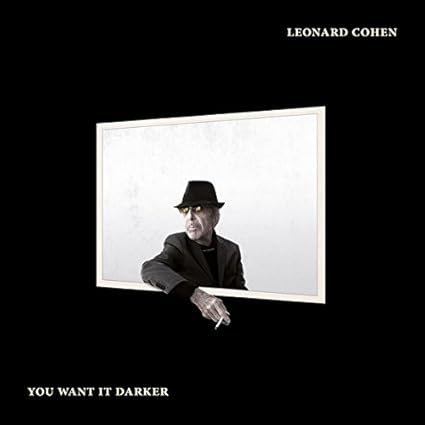
Leonard Cohen
You Want It Darker |
過去作と比べて最もポップに感じた遺作。フィル・スペクターと作ったあれよりも、ずっと聴きやすかったのは世代のせいかな。自分の初コーエンはコイルの「フー・バイ・ファイア」で、そこから原曲と過去作を聴いてみたはいいものの、老成の先を行きすぎて鎮座した世界にハマれるわけもなく。忘れた頃に聴き返しては、生と死、セックスと喪失を中心に廻り続ける歌に沈んでしまうが、音楽以外の景色を積み重ねてみれば、わずかながらにその渦の目を捉えることができるようになった気もする。本当に微々たる変化だが、今後も続いていくものなのだろう。作品が残るとは、こういうことなのだと思う。
他国の言語、文学、宗教、歴史などを調べていくことで、自分より外の世界が認知できるようになってくる。どこか遠くの果ての果てで歌われている音楽で終わらせられない程度にはコーエンも言葉も複雑なはずだ。人は皆闇の中にいるのだとも言いたげなジャケットだが、コーエンはその因果の中からもタナトスやエロスを見出して、諦観だけではまとめきれない、人の生を歌ってきたのだと思う。人生の不文律、選べない誕生、使命、受難、矛盾、それらの放棄すらも闇の中にあるとしたら、途端に雄弁なアルバムに感じるようで...。理解し、付き合っていくには今まで生きてきたよりも長い年月が必要かもしれないが、今はコーエンの官能的な声と美しい伴奏によって、未熟で後ろめたい自分語りに走ってしまう時間が得られることを幸運と思いたい。 |

John Duncan
Bitter Earth
|
米前衛音楽の大家、ジョン・ダンカンの新作はカバーソング集である。ノイズも含めて音数は極小だが、ガン・クラブのカバーはヴェルヴェッツの「ギフト」のようで、ここにもダンカン氏のルーツが表れている。個々の音は多くの協力を得たもので、片手間で用意されたわけではなく、ジム・オルークや石橋英子といった面々が並ぶクレジットを見てもそれは明らかだ。コルトレーンの仕事でも知られる「オータム・セレナーデ」は中国の管楽器であるスオナが使われているなど、ただのカバーではない。曲に対する思い入れやイメージだとか、抽象的な情景をクッションにするのではなく、ただ音の鳴りを受け入れる時間を求めているとも言える(原曲とかけ離れてるから無問題だが)。
素敵なのは、手拍子やコーラス、タンバリンといった最小限のリズムを従えるダンカン氏のボーカルが、あまりにグルーヴィーで、ちゃんと歌がアルバムを牽引しているところだ。「ダーク」(ペル・ウブ)はその最たるもので、B面のはじまりにしてアルバムのクライマックス。原曲を知るよりも先にここで聴けて幸運だとすら思う。
俗に言う歌唱力とは違う歌の上手さがあり、歌というよりはヴォイス・パフォーマンスと書いた方が近いかもしれない。こんな実験は何度も通過しているはずだが、過去に通ってきた曲を介することで新たな発見と再認を見つけているのだと思う。過去は後から現在に重なり、先を導いてくれることもある。それに気付くための術が、自分で歌ってみることなのだろう。シングルも切られているそうだ。
|